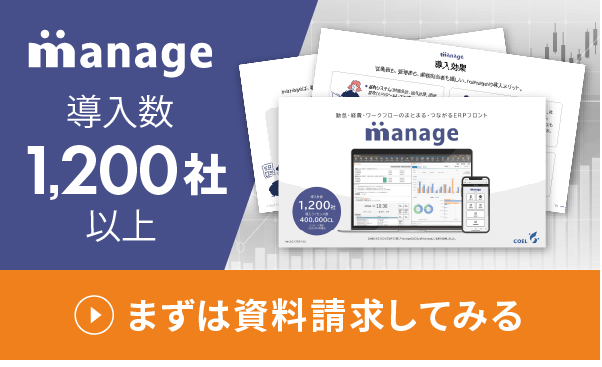ひとり親への配慮とは?
労働者がひとり親家庭の親である場合であって、労働者が希望するときは、子の看護等休暇の付与日数に配慮することが望ましいとされています。
育児・介護休業法が2025年に改正!社労士が改正内容を解説

2025年に育児・介護休業法が2度にわたり改正されます。
これに伴い、企業の人事・労務担当者には、就業規則の見直しに加えて、介護離職を防止する観点からも、支援が必要な従業員に対して職場環境の整備が求められます。
本記事では、改正の具体的な内容に加え、介護休業の対象者や「要介護」の判断基準について、社労士の視点からわかりやすく、丁寧に解説いたします。
目次
育児・介護休業法が2025年4月と10月に改正

育児・介護休業法等の法改正が可決となり、2025年(令和6年)の4月1日と10月1日に、段階的に施行されます。
今回の改正の主な変更ポイントは、下記の3つです。
- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
育児・介護休業の取得対象拡大や条件の緩和が行われ、企業に対しても休暇を取得しやすい環境整備が求められます。
今回の改正は事業規模を問わず、「義務」とされているものが多いため、すべての企業が対象となります。
育児介護休業法とは
育児介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)は、平成3年に制定された育児休業法がその前身としています。
平成11年には介護休業制度が義務化され、法律名も現在の「育児介護休業法」へと改称されました。
この法律は、職業生活と家庭生活の両立を支援するの制度として位置づけられています。
今回の改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにすることを目的としており、柔軟な働き方の実現が大きな柱となっています。
2025年4月の法改正一覧
- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
- 育児のためのテレワーク導入
- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大(次世代育成支援対策推進法の改正)
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和【労使協定を締結している場合は就業規則の見直し】
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護職防止のための個別の周知・以降確認
- 介護のためのテレワーク導入
2025年4月1日より施行される改正内容では、育児・介護休暇の取得対象の拡大や条件の緩和があり、企業には労働環境の整備が求められます。
また、一部の内容では、就業規則の変更対応が必要となります。
2025年10月の法改正一覧
- 柔軟な働き方を実現するための措置等
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
2025年10月1日より施行される改正内容では、3歳~小学校就学前の子を養育する従業員に対して、柔軟な働き方を実現するための措置が義務付けられます。
併せて、従業員への適切な周知も必要となります。
2025年4月の法改正の改正内容
| 改正内容 | 改正箇所 | 義務 |
|---|---|---|
| 子の看護休暇の対象拡大と取得条件の緩和 | ・小学校3年生修了までに対象拡大 ・取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式、卒園式」が追加 ・労使協定による除外規定から雇用6か月未満を除外 ・名称が子の看護等休暇に変更 | 【義務:就業規則等の見直し】 |
| 所定外労働の制限の対象拡大 | ・小学校就学前の子を養育する労働者に対象拡大 | 【義務:就業規則等の見直し】 |
| 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 | ・テレワークが追加 | 【選択する場合は就業規則等の見直し】 |
| 育児のためのテレワーク導入 | ・3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずる | 【努力義務:就業規則の見直し】 |
| 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 | ・従業員数が300人超の企業に対象拡大 | 【義務】 |
| 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 | ・労使協定による除外規定から雇用6か月未満を除外 ※労使協定での除外条件は子の看護等休暇と同じ | 【労使協定を締結している場合は就業規則の見直し】 |
| 介護離職防止のための雇用環境整備 | ・介護休業や介護両立支援制度の申し出が円滑に行われるようにするための措①~④いずれかの措置を講じる ① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施 ② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置) ③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供 ④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知 |
【義務】 |
| 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 | ・介護に直面した旨を申し出た労働者に対して、周知事項と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用意向の確認を個別に行う | 【義務】 |
| 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供 | ・介護に直面する前の早い段階での介護休業や介護両立支援制度について情報提供を行う | 【義務】 |
| 介護のためのテレワーク導入 | ・要介護状態の対象家族を介護する労働者に対しテレワーク選択措置を講じる | 【努力義務:就業規則等の見直し】 |
2025年10月の法改正の改正内容
| 改正内容 | 変更内容等 | 義務 |
|---|---|---|
| 柔軟な働き方を実現するための措置等※1 | 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して5つの選択から2つ講じる ① 始業時刻等の変更 ② テレワーク等(10日以上/月) ③ 保育施設の設置運営等 ④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年) ⑤ 短時間勤務制度 |
【義務:就業規則等の見直し】 |
| 仕事と育児の両立に関する個別の意見聴取・配慮 | 子が3歳になるまでの適切な時期に※1で選択した制度の周知と制度利用の確認を個別に行う | 【義務】 |
柔軟な働き方を実現するための措置で②テレワークを選択する際、週4日勤務の方の場合は8日以上と基準を設けることは差し支えありません。
また、⑤短時間勤務制度を選択する場合、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含めることが必要です。
さらに、従業員がこの制度を利用するにあたっては、週の全てを短時間勤務とせず、「木曜日」のみ短時間勤務とするといった柔軟な選択も可能です。
柔軟な働き方を実現するための措置は、子が3歳になるまでの適切な時期(1歳11カ月に達した日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日までに周知が必要です。
柔軟な働き方を実現するための措置の周知
| 周知時期 | 労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間(1歳11カ月に達した日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日まで) |
|---|---|
| 周知事項 | ① 対象措置の内容(両立支援制度等のうち2つ以上) ② 対象措置の申出先(例:人事部など) ③ 所定外労働(残業免除)、時間外労働・深夜労働の制限に関する制度 |
| 意向聴取の方法 | ①面談 ②書面交付 ➂FAX ④電子メール等のいずれか 注意:①はオンライン面談も可能③④は労働者が希望した場合のみ |
仕事と育児の両立に関する個別の意見聴取・配慮義務化
|
対象労働者 |
① 本人または配偶者が妊娠・出産等の申出をした労働者 ② 子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間(1歳11か月に達した日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)である労働者 |
|---|---|
| 聴取内容 | ④ 勤務時間帯(始業及び終業時刻) ⑤ 勤務地(就業場所) ⑥ 両立支援制度等の利用期間 ⑦ その他仕事と育児の両立の支障となる事情の改善に資する就業の条件 |
| 意向聴取の方法 | ①面談 ②書面交付 ➂FAX ④電子メール等のいずれか 注意:①はオンライン面談も可能③④は労働者が希望した場合のみ |
事業主は、意向の聴取をした労働者の就業条件を定めるにあたっては、聴取した労働者の仕事の育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
配慮の内容は、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度等の利用の利用期間の見直し、労働条件の見直し等です。
介護離職防止のための情報提供・意向確認など内容比較
| 改正内容 | 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等※1 | 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供※2 |
|---|---|---|
|
対象者 |
介護に直面した旨の申出をした労働者(申し出:労働者が通知した) | ①労働者が40歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度(1年間) ②労働者が40歳に達した日の翌日(誕生日)から1年間 |
| 周知確認等 | 周知および意向確認 | 情報提供 |
| 各事項 | ①介護休業に関する精度、介護両立支援制度等 ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ➂介護休業給付に関すること ※2では併せて介護保険制度について周知することが望ましい |
|
| 方法 | ①面談 ②書面交付 ➂FAX ④電子メール等のいずれか 注意:①はオンライン面談も可能 ※1では➂④は労働者が希望した場合のみ |
|
※介護両立支援制度等とは、I.介護休暇に関する制度、II.所定外労働の制限に関する制度、III.時間外労働の制限に関する制度、IV.深夜業の制限に関する制度、V.介護のための所定労働時間の短縮等
※意向確認措置は、事業主から労働者に対して、面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかの措置を行うことで意思確認の働きかけになります。
介護休業の対象者と基準
介護休業は、対象家族であって、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある者(障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む※改正)を介護するための休業です。
対象家族には、以下が含まれます(同居の有無は問いません)
「介護休業の対象家族」
- 配偶者
- 父母
- 子
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
- 配偶者の父母
常時介護の基準については、厚生労働省で定める判断基準をご参照ください。
介護に関する制度の周知・情報提供の重要性
介護に直面する前の早い段階での情報提供では、各種制度の趣旨や目的を踏まえることが望ましいとされています。
【介護休業制度の目的】
介護休業制度は、介護の体制を構築するために一定期間休業する場合に対応する制度です。
市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーへの相談をはじめ、介護の分担の検討、民間事業者・ボランティア・地域サービスの活用など、利用できる支援を探すことが含まれます。
【介護休暇制度の目的】
介護休暇制度は、介護保険の手続きや要介護状態にある家族の通院付き添いなど、日常的な介護のニーズにスポット的に対応することを目的としています。
介護について調べる機会がない方にとっては、こうした制度の趣旨や利用方法を十分に理解していないことが想定されます。
そのため、事前に情報を提供することで、介護が必要になった際に慌てることなく適切な対応ができるようになります。
また、職場や家庭での介護に関する準備を進めることで、介護と仕事・育児の両立についてもスムーズに対応できる可能性が広がります。
特に、介護休業制度の利用には事前の申請が必要となるため、早めの情報収集が重要です。
自治体や企業の制度を把握し、自身の状況に適した選択肢を検討することが、負担を軽減するための第一歩となります。
育児・介護休業法改正で企業に求められる対応

今回の法改正に対応した就業規則の変更が必要になります。
就業規則の改正手順は以下4点となります。
- 就業規則の変更
- 労働者の意見を確認する
- 就業規則の変更内容を周知する
- 休暇の適切な管理
①就業規則の変更
具体的なケース別の就業規則の変更例と解説があります。
規定変更の際にフォーマットとして使えますので、ぜひご活用ください。
②労働者の意見を確認する
「就業規則変更の際の労働者への意見徴収」
- 労働者の過半数で組織された労働組合がある場合→その労働組合の意見を提出
- 労働組合がない場合→労働者の過半数を代表する物の意見を提出
就業規則の変更には、労働者の意見徴収が必要です。
この手続きは、従来の就業規則の変更と同じ方法で行うことができます。
労働基準法90条では、使用者は就業規則の作成又は変更にあたり、労働者代表の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
この手続きを適切に進めることで、就業規則の変更が行えます。
意見徴収がない場合や、就業規則の変更内容を従業員に周知していない場合は、変更が無効となる可能性がありますので、注意しましょう。
また、就業規則変更届は、労働基準法109条に基づき、原則5年間(当面の間は3年)は保管する必要があります。
③就業規則の変更内容を周知する
「就業規則変更の周知方法」
- 労働者への直接配布(紙または電子データ)
- 職場内の掲示・備え付け(労働者がいつでも確認できる場所)
- 電子媒体での公開(常時モニターで表示するシステムなど)
就業規則の変更に関する周知は、施行日と同じ日に行っても問題ありません。
重要となるのは、従業員全員が「就業規則の場所を知っている」「就業規則はいつでも見られる状態にある」ということです。
例えば、「社員すべてがアクセスできるフォルダに就業規則を保管し、就業規則の変更箇所があった場合に、変更箇所についてメールで一斉通知する」といった手段が考えられます。
このように、従業員が変更内容を認識できる仕組み作りが必要です。
④休暇の適切な管理
法改正に伴い、育児や介護などの休暇管理を適切に行うことが求められます。
特に育児・介護休業法の改正では、休暇の取得日数の管理や、テレワークなど新たな働き方を導入するための管理が必要になります。
アナログな管理方法では人為的なミスが発生しやすく、確認の手間や申請書の受け渡しなどの負担があるため、法令に対応した勤怠管理システムの導入をおすすめします。
ただし、システムを導入しただけで安心とは限りません。
法改正や社内規定の変更に応じて、自社に合わせたシステムの調整が必要になる場合もあります。
そのため、サポート体制が充実しているシステムを選ぶことで、より安心して運用できるでしょう。
従業員が育児・介護休業を取得しやすい環境を整えよう

各制度を準備するだけでなく、適切な周知を行い、従業員が自身の権利を十分に理解し、安心して行使できる環境を整えることが重要です。
個別周知と意向確認であれば、対象措置の申し出が円滑に行われることを目的としていますが、従業員が取得や利用をためらうような手段や方法になっていないか十分に配慮する必要があります。
manage勤怠システムでは、適切な休暇を管理するだけでなく、従業員の制度への理解が不十分な場合でもアシストする「業務ナビゲーション」機能があります。
こちらを活用すると、業務担当者が設定した質問に対し、従業員は介護休業の対象に、該当するかどうかを確認して適切な申請を出すことができます。使い方は簡単で、「業務ナビゲーション」の質問に対し、はい・いいえを選択するだけで対象の申請書に誘導してくれます。
従業員が育児・介護休業を取得しやすい環境づくりにはぜひともmanage勤怠をご活用ください。