人件費に含まれるもの
- 毎月の給与・各種手当
- 年間の賞与
- 役職に合わせた役員報酬
- 社員旅行といった福利厚生費
- 社会保険・労働保険などの法定福利費
- 退職金・退職一時金
- 交通費や出張費

人件費率が知りたいけれど、基準値や自社にとっての適正値がどの程度になるのかわからず悩んでいませんか?
人件費は、従業員に支払われる経費であり、会社によって内訳はさまざまで適正値も異なります。
しかし、業界別の基準値はある程度決まっており、実際に人件費率を算出した際に大幅に超過しているのであれば改善が必要です。
本記事では、人件費に含まれる費用の種類から業界別の目安、人件費の計算方法について解説していきます。
目次
人件費に含まれるもの
人件費=給与+各賞与+役員報酬+福利厚生費・法定福利費+各退職金+現物支給費
人件費に含まれるのは、会社が従業員に対して支払う給与や賞与、福利厚生などの費用となります。
給与や賞与、福利厚生費などは、会社の業績によって見直しができますが、法定福利費や交通費・出張費は決まった額の支給を行います。
このように、人件費の種類はいくつかありますが、見直しできるものは一部となるため、どのような人件費がかかっているのか知っておくことが大切です。
ここからは、具体的にどのような経費が人件費に含まれるのか、それぞれ解説していきます。
従業員に支払われる給与や各種手当、パート・アルバイト・業務委託での報酬は人件費に該当します。
給与には基本給や歩合給、報酬のほかに、各種手当である住宅手当、扶養家族手当、交通費なども含まれます。
残業手当や休日出勤手当も各種手当に該当し、もし時間外手当の割合が多いのであれば、労働時間を短縮出来るように業務の見直しが必要です。
手作業の業務を自動化させる・案件の工数を見直して従業員の能力やリソースが足りているのかを確認するなど、対策をしましょう。
給与とは別で、臨時報酬として年に数回支払われる賞与も人件費として扱います。
賞与は一般役職の従業員のみに支給されるもので、業績に応じて支給額を決めるのが一般的です。
年間の賞与があることで、従業員のモチベーションが向上し、業務品質の向上が見込めますが、業績が悪い中多くの額を支給してしまうと利益を圧迫します。
賞与における人件費の見直しでは、業績に見合った額を支給しているのかどうかで判断しましょう。
たとえば、企業によっては利益の1/3を賞与原資としている場合などがあります。
しかし、高収益企業でもない限り賞与原資が少なくなってしまうため、労働分配率を基準とするなど、自社に合ったルールを決めておくと良いでしょう。
役員報酬は、従業員の賞与とは分けて扱われているもので、定額同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与などがあります。
税法でも、役員報酬は従業員へ支払われる賞与とは分けて扱われるため、人件費の見直しの際も一緒にしないようにしましょう。
役員報酬でも、業績に合った額が支給されているのかを確認し、必要に応じて見直しを行うなど、対策を講じることが求められます。
福利厚生の詳細は企業によってさまざまですが、社員旅行や優待券など、従業員全員を対象に提供しているもの全般が人件費となります。
このとき、健康診断の実施は義務ではあるものの、法定福利厚生には含まれないため、福利厚生費として扱います。
福利厚生の導入は任意となりますが、従業員のモチベーションの向上や健康に働いてもらうために必要な経費です。
ただし、多すぎても会社の負担になったり福利厚生費として認められなかったりするので、常識的な範囲で費用設定しましょう。
社会保険や労働保険などは法定福利費といい、福利厚生費とは異なり会社が費用の一部を負担することが義務付けられています。
社会保険や労働保険は、業種や従業員の給与額によって金額が変わり、必ず会社が一部を負担することが義務となっているので、削減するのは難しいです。
法定福利費は削減できない必要経費としてカウントし、人件費の見直しをするのであれば、給与や福利厚生費などから行いましょう。
退職金や退職一時金、退職年金も、従業員に支払われるものなので人件費として扱われます。
退職金や退職年金の算出は、就業規則や退職金規定などをもとに取り決めを行うことが基本となります。
人件費削減を検討するのであれば、人事担当や経営陣はどのような予算管理を行っているのかを把握したうえで人件費に含めることが重要です。
交通費や出張費も人件費として扱われ、通勤手当や出張手当として支給する場合は、給与に含まれます。
別途、旅費交通費の名目で計上することも可能です。
また、通常は金銭で支払いますが、定期券などの物品で支給している場合、給与に含まれる現物支給費の扱いになります。
交通費と出張費は上限を決めるなどの対策をし、過剰な支払いにならないよう検討が必要です。
現物支給費には他にも食事代や社宅費用といった、給与に含むこともできれば福利厚生費で扱うことも可能な費用があります。
勘定科目をどう分けるか、自社で明確なルールを設けておきましょう。
| 業種名 | 人件費率の目安 |
|---|---|
| 製造業 | 20.7% |
| 情報通信業 | 30.7% |
| 小売業 | 13.3% |
| 卸売業 | 7.0% |
| 飲食業・サービス業 | 37.0% |
人件費率の目安については、製造業20.7%、情報通信業30.7%、卸売業7.0%と、業界によって大きく異なります。
たとえば、業務の自動化が難しい飲食業・サービス業では、どうしても手作業での対応が必要なため、人件費率は高くなりやすいです。
しかし、同じ業界でも無人レジを導入していたり、回転寿司店のように自動化されていたりする場合、人件費率は目安よりも下がります。
また、人件費率が低ければ良いというわけではなく、利益に対して従業員への還元が少なくなっている可能性もあるため注意が必要です。
そのため、あくまでも業界の目安として参考にしつつ、自社の業務内容や利益、売上などをもとに人件費率の削減を検討しましょう。
※e-Stat「政府統計の総合窓口」の発表している、令和3年確報(令和2年度決算実績)のデータをもとに、業界別の人件費率の目安を算出しています。(「法人計」の販売費及び一般管理費「のうち、人件費」と「労務費」を足して算出)
e-Stat「政府統計の総合窓口」の発表している、令和3年確報(令和2年度決算実績)のデータをもとに、IT業の場合の人件費率を計算していきます。
まず、従業員数51名以上の情報通信業の場合、売上高が「7559052.874」、人件費が「1169684.265」、労務費が「1066916.456」(どちらも単位は百万円)です。
人件費率の計算式に当てはめると結果は約29.5%となり、業界別人件費率の目安として算出されている「30.7%」よりもやや低くなります。
手作業の業務を自動化するなど、業務効率化が進められている企業では、目安よりも人件費率は下がる傾向にあります。
まずは、業務内容や自社の人件費率と比較しながら、人件費率の改善を進めるようにしましょう。

人件費率には、売上高人件費率と売上総利益人件費率の2種類があり、目的に合わせて計算方法を使い分けます。
売上高人件費率は売上高に対して、売上総利益人件費率では売上総利益に対しての人件費率となります。
売上高で算出した場合には、簡易的に人件費率を出すことができ、売上総利益だとより正確な人件費率の算出が可能です。
大まかでも現況の数値を早く把握したいときは売上高を使い、実際に人件費率の削減を進める際には売上総利益を使うなど、目的に合わせて計算方法を変えましょう。
売上高を使った計算では、簡単に人件費率を出すことができ、企業の売上に対してどれだけの割合を人件費が占めているかの指標となります。
たとえば、売上高が1,000万円で人件費が300万円の場合、人件費率は「300万円 ÷ 1,000万円 × 100 = 30%」となります。
人件費率の数値が高ければ高いほど、人件費の負担が多いということになるので、企業として改善が必要です。
ただし、業種によって適正な人件費率は異なるため、数値を見て高い・低いを判断するのではなく、まずは適正値かどうか確かめましょう。
粗利益である、売上総利益から人件費率を算出する方法では、売上原価が含まれないのでより正確な人件費率の算出が可能です。
売上総利益が500万円で人件費が200万円の場合、人件費率は「200万円 ÷ 500万円 × 100 = 40%」となります。
売上から売上原価を引いた利益である、売上総利益に対する人件費の割合を示す指標となるので、収益と人件費のバランスをより正確に把握できます。
売上総利益人件費率が高い場合、売上に変動があっても人件費が固定費として出ていくため、利益がしっかりと確保できません。
そのため、売上総利益に対する人件費の見直しをするうえで、たとえば、労務費がかさむことを防ぐために、従業員が効率的に働けるような環境かどうか検討することが大切です。
自社の人件費が適正かどうか確かめるには、人件費率や労働分配率、一人当たりの売上高をもとに確かめます。
実際に人件費率を計算して、自社の人件費率がどの程度になっているのか確認し、同業界と比較していきます。
たとえば、サービス業では人件費率が高くなる傾向がありますが、製造業や小売業では比較的低いことが一般的です。
業種によって人件費率が異なるため、業種の基準値よりも大幅に人件費率が高い場合は、人件費の見直しを行うようにしましょう。
しかし、無理に費用を削減しようとすると、従業員への還元が減り、モチベーションや品質の低下につながる可能性があるので注意が必要です。

労働分配率とは、企業の生み出した付加価値に対しての人件費の割合のことを指しています。
ここでの付加価値の計算には「控除法」と「加算法」があり、目的に合わせて計算方法を変えてみましょう。
労働分配率が高い場合、付加価値を得るために多くの人件費をかけており、利益の確保ができていない可能性があります。
もし、労働分配率が低いのであれば、少ない人件費で付加価値を得ていることになりますが、従業員に還元されていないとも受け取れます。
ただし、労働分配率の基準値は業種によっても異なりますので、大きく乖離しているかを確認したうえで、改善していきましょう。
労働分配率は、人件費と付加価値を使って算出できるもので、従業員にどれだけ付加価値を分配されたのかを示しています。
たとえば、付加価値が1,000万円で人件費が300万円の場合、労働分配率は「300万円 ÷ 1,000万円 × 100 = 30%」です。
労働分配率が上がれば給与や福利厚生などで還元ができており、下がっていれば労働効率がいいといえます。
ただし、労働分配率が上がると人件費がかさむので経営が悪化する恐れがあり、下がると従業員へ還元できていない可能性があります。
労働分配率はバランスが重要となるため、業種ごとの平均値や人件費率と合わせて確認しましょう。
| 業種名 | 労働分配率の平均 |
|---|---|
| 製造業 | 64.3% |
| 情報通信業 | 56.9% |
| 小売業・卸売業 | 70.3% |
| 飲食業・サービス業 | 74.9% |
厚生労働省が発表している令和4年版 労働経済の分析では、労働分配率の統計データが掲載されており、卸売業・サービス業では水準が高い結果が出ています。
人手による業務が必須となる卸売業・サービス業では、どうしても労働分配率が高くなりやすい傾向にあります。
また、情報通信業では、業務の自動化を進めやすいため、労働分配率は56.9%と卸売業・サービス業に比べると水準は低めです。
ただし、労働分配率については、コロナ禍やDXの推進などの影響など、数値は変化しやすいので、状況に応じて対策が必要となります。
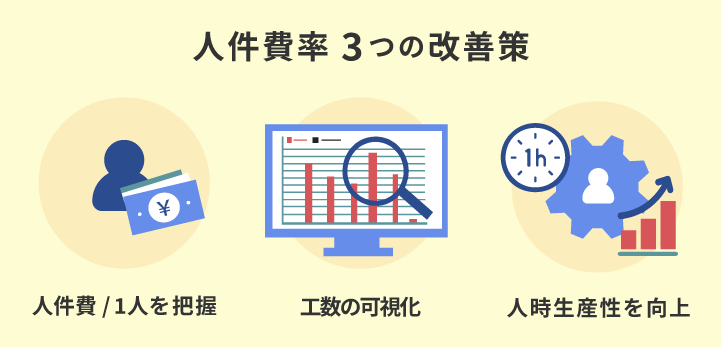
人件費率を抑えるのであれば、売上を上げるもしくは人件費を削減するという方法があります。
自社でかかっている人件費を洗い出しつつ、生産性が向上するようなシステムの導入などを検討しましょう。
ただ、人件費を削ろうとする場合、従業員への還元が少なくなってしまい、不満の増加により必要な人材に離職されてしまう可能性があります。
そのため、売上の向上につながるような改善を取り入れ、従業員への還元も確保できるような対策が必要です。
まずは、人件費の合計を従業員数で割り、1人あたりの人件費を洗い出しましょう。
その後、給与や福利厚生、賞与などが適切な額になっているか確認し、人件費率が高い場合は見直しが必要です。
また、残業代や休日出勤手当が多い場合は、業務効率化や人員調整などの対策を検討します。
この際、工数管理を行うことで、従業員が抱えている業務量や1人あたりの労務費を正確に把握しやすくなります。
案件ごとに従業員の工数を明確にすることで、1人当たりの作業量が把握でき、労務費に対して利益が確保できているか確認できます。
案件が赤字に進行していることが途中でわかれば、利益が確保できるように修正することも可能です。
また、工数の詳細な把握により、どの案件で人員が不足しているか、必要な人員が確保できているかが明確になります。
従業員の能力や作業量を把握したうえで適切に配置できれば、業務の効率化となり利益向上にもつながるため、案件ごとの工数管理を行いましょう。
人時生産性とは、従業員1人が1時間でどの程度の利益を生み出しているかの指標で、数値が高ければ短時間で多くの利益を出していることになります。
人時生産性を向上させるには、手作業の業務を自動化させたり、業務負担を軽くするシステムを導入したりすることで実現が可能です。
従業員1人ひとりが短時間で多くの利益を生み出せると、会社全体で生産性が向上し、その分多くの還元ができます。
会社にとっても従業員にとっても、大きなメリットになるため、人時生産性を向上させられるように業務負担の多い箇所を洗い出して改善していきましょう。
人件費率を知ることにより、売上に対する人件費の割合を把握できるため、利益を確保するための対策を取れます。
もし、残業手当や休日出勤手当が多いのであれば、従業員の作業効率化を図ることで、人件費率の改善が見込めます。
このとき、工数の可視化を行うことで、従業員1人ひとりの作業量や能力を把握し、適切な業務への割り当てが可能です。
まずは、自社の人件費率を算出したうえで、工数管理も行いながら従業員が自身の能力を存分に発揮できるような環境を整えましょう。
弊社の提供するmanage 工数では、パソコンやスマートフォンから利用できるため、業種を問わずに導入しやすいのが特徴です。
さらに、登録された工数のデータは、円グラフや棒グラフで表示ができ、単価マスターを登録しておくことで原価表も確認できます。
従業員ごとの原価を適切に把握し、工数管理でリソースも適宜確認することで、最大限利益を確保できるような対策が可能です。
無料トライアルや資料をご用意していますので、具体的な操作方法が知りたいという方はぜひお問い合わせください。